遺言書の書き方
よく利用される遺言の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。遺言者が生前に財産の分配方法を決めておいた方が、残された人々が無用な諍いをすることもなく、仲の良さを保てる場合は多々あります。書いて後悔した人はいない、とも言われる遺言書です。書いてみようかと少しでも頭をよぎった場合は本気で検討されてみることをお勧めします。
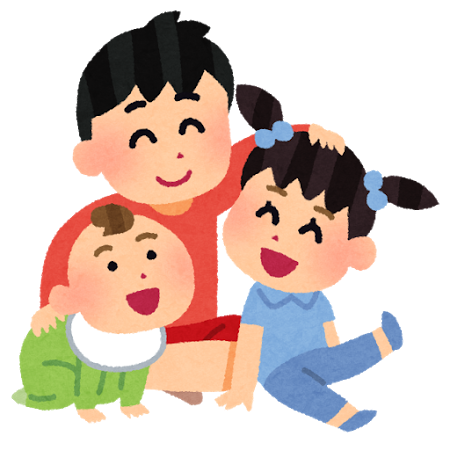
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆で書き、押印した遺言書です。全文自筆が条件で、ワープロ、代筆、署名のみ自筆などは原則として認められません(財産目録はワープロ作成可)。また、夫婦等といえど、二人以上の人が同一の証書で遺言を書く共同遺言は認められていません。何が共同遺言にあたるかは解釈の余地はありますが、紛争を避けるため、一人で独立した遺言を書くのが良いでしょう。
遺言書の日付は、年月日が特定できることが必要です。年月だけ、あるいは『吉日』などの書き方は無効となります。氏名は、遺言者が特定できることが必要です。戸籍上の正しい氏名を書くのが書き方として無難です。住所の記載は要件ではないのですが、遺言者の特定のため、住所を記載した方が良いでしょう。相続登記など、後日の手続きがスムーズになります。
遺言書に押印する印鑑には決まりはありませんが、紛争を避けるため、実印での押印が望ましいでしょう。遺言書が数ページにわたる場合は、ページとページの綴り目に契印をした方が良いでしょう。
財産に関することだけでなく、気持ちなどを書き添えても構いません。どうしてこのような財産の分配を決めたのか、などの理由も書いた方が残された人々の納得が得られるという面もあります。
また、令和2年7月10日より、遺言書の保管制度が始まりました。全国の法務局が遺言書保管所となり遺言書を保管します。紛失の危険や成立の適正さに対する信用を考えると、作った自筆証書遺言書の保管は、こちらを利用した方が良いでしょう。自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、遺言書保管所において遺言書を保管すると、この手間を省くことができます。顔を合わせたくない親族や、連絡のとれない親族がいる場合は、この検認手続きは少し面倒な手続きです。ただし、公正証書遺言のような公証力はありません。
公正証書遺言
遺言書の内容が複雑である場合、または遺産をめぐり相続人間に深刻な争いが予想される場合、あるいは確実にスムーズに遺言書の内容が実現されて欲しい、このような事情のある場合は公正証書遺言をお勧めします。